


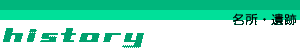 |
| 木ノ芽峠 | ||
 |
||
| 福井県を嶺北と嶺南に分ける地であり、昔から北陸道として往還の道となっていました。峠には1200年の間、越前の玄関口として番所の役割を果たした茅葺き屋根の茶屋の姿が今も残っています。 この一帯は度重なる古戦場の舞台となり、一向一揆の頃の城址も多く、歴史的にも興味深い峠です。 |
||
| 言奈地蔵 | ||
 |
||
| 昔、権六という馬子が旅人を殺し金を奪いました。そばに地蔵がいたので「地蔵言うなよ」と口止めしたところ、「地蔵言わぬが我れ言うな」と言われ山を降りました。 その後、この峠で若い旅人と出会い、それがかって殺した旅人の息子であると知り、因縁におののいた権六は自ら仇を討たれたという伝説が残る不思議な地蔵。 |
||
| 板取の宿 | ||
 |
||
| 1578年、柴田勝家が栃ノ木峠越えの北国街道を改修して以来栄えました。北国街道の入り口として初代福井藩主結城秀康は番所を設け旅人を取り締まったところで、3軒の問屋、7軒の旅籠、6軒の茶屋があり、参勤交代の殿様が一服する場所でもありました。 現存する茅葺き屋根は、甲(かぶと)造り型でとても珍しいものです。 |
||
| 今庄宿 | ||
 |
||
| 今庄の町並 | ||
 |
||
| 京藤家 | ||
| 木ノ芽峠を越える北陸街道と栃ノ木峠を越える北国街道の二つの峠道が出会う今庄宿は初代福井藩主結城秀康の時代に整備され、江戸時代には越前で最も繁栄 した宿場です。 今でも通りには、当時にぎわった京藤家など異彩を放つ建物も残り、なお昔ながらの面影を残し、素朴な趣を漂わせています。 |
||
| 燧ケ城址 | ||
 |
||
| 1183年、木曽義仲が築城。義仲の軍勢は、平氏軍10万と戦った際、平泉寺の長吏斉明の裏切りにより敗北したと伝えられています。杣山城と金ケ崎城とともに北陸の関門を制する重要な場所でした。源平盛衰記には「北陸道第一の城郭なり」と歌われ、今も砦や本丸跡には石垣、その周辺には空掘や切掘などが残っています。 | ||
| 夜叉ケ池 | ||
 |
||
| 福井県、滋賀県、岐阜県の3県にまたがる三国ケ岳北側、ブナ林の原生林に囲まれた標高1,100mの山頂にあり、日野川の水源といわれています。池の周囲は545m、古来より龍神伝説、雨乞いの池として名高い。一帯にはシャクナゲやニッコウキスゲなど高山植物が群生、ここを唯一の生息地とするヤシャゲンゴロウをはじめ野生動物も多く生息しています。 毎年6月第一日曜日には、山開きの神事が行われます。 |
||
| 宅良周辺 | ||
 |
||
| 慈眼寺 | ||
| 全国古刹のひとつに数えられる慈眼寺は、かつては全国に天真派千百余の末寺を持つ大寺でした。 | ||
 |
||
| 伊藤氏庭園 | ||
| 伊藤氏庭園は享保年間(1716~1735)当時流行した庭園図本に基づいて造られた庭園であり、昭和七年国の名勝に指定されています。 | ||
 |
||
| 蓮如上人旧跡 | ||
| 下長谷の洞窟 | ||
 |
||
| 延元二年(1337)、金ケ崎城落城の際に気比神宮の神官が春宮恒良親王をかくまった場所といわれています。 長い年月をかけて少しずつ波が岩を削りできた海食洞で、入口は広く奥は狭くなっています。奥行きは約25mあり、最奥部に「延元二年正月二十一日 二ノ宮恒良自供十一人」と彫字があります。 |
||
| 馬借街道(西街道) | ||
 |
||
| 中世の朝倉氏が支配していた時代から明治初期に至るまで、北前船と並ぶ交通の主役として、河野~敦賀の航路を経て大阪、京都方面へ通じる重要な役割を果たした街道です。 武生(現在の越前市)市街地から中山梨木峠を通り河野(今泉)へ抜ける約15㎞の街道沿いには、石畳や排水溝、石仏石碑、番所跡などが往時の面影を残しています。 |
||
| 白竜の滝公園 | ||
 |
||
| 風光明媚な景色が続く越前加賀海岸国定公園内(国道305号)の南越前町と越前町の境に位置する緑地公園。 かつて出雲の国から船に乗った19人が糠浦に漂着した際、その船を守った竜が山頂にある暖かい池で体を癒すために昇ったという伝説が残ります。 木々の間から流れ落ちる水しぶきが清涼感を与えてくれるマイナスイオンあふれる公園です。 |
||
| 役の行者 | ||
 |
||
| 南越前町上牧谷の金毘羅堂に安置されている日野山信仰と関わりの深い像。役の行者は「役の小角(おづね)」といい、大和の国に生まれ、三宝を信奉し、最後は仙人になり昇天したと言い伝えられています。 | ||
| 妙泰寺 | ||
 |
||
| 永仁二年(1294)日像菩薩開山。日蓮の遺命により布教のため京都へ上る途中、この地に足を止めた日像が、「この山身廷山に相似たり、他日法華興隆の地とならん。」と健立された寺である。以来七百年北国身廷と称し、門流四ヶ聖跡の霊地として栄えてきた。福 井藩主結城秀康や松岡藩主松平昌勝も深く帰依し神田などを寄進している。幕末の歌人橘曙覧も、少年時代にこの寺で修行している。七福神祭りは全国でも珍しい奇祭である。 | ||
| 杣山城跡 | ||
 |
||
| 昔より北陸道の軍事的拠点として重要視されてきました。特に南北朝時代に南朝方についた豪族瓜生保氏が足利方の大軍を迎えて激戦を繰り広げた本拠地です。 中央登山道の入り口にある一の城戸と阿久和集落の入り口にある二の城戸が残る城跡には数々の史跡が残っています。国の指定を受け現在、遺跡発掘が進められています。 |
||
| 鵜甘神社 | ||
 |
||
| 山王山の中腹にある杣山式内総社鵜甘宮は、新田義貞が戦勝祈願のため参拝して神領や神輿を寄進。飛鳥時代白鳳二年(651)三月創建の古社である。県の重要文化財にも指定されている社宝の王の面は県内でも最古の正安4年(1302)の貴重な作品です。 | ||
 |
||
| 社務所の脇の木戸をくぐると目の前に広がる、鵜甘神社の神宮が所有する庭園は杣山池泉蓬莱鶴亀園と呼ばれ、江戸時代中期の明和四年(1767)に京都の庭師によって作庭されたものである。 この庭には山の斜面を利用して、その裾野に池泉が横たわり亀島が浮かぶ。以前は亀島と向き合うように、翼を広げた鶴を模したマツがあったそうだが惜しくも枯死したとのこと。杉林とモウソウダケの竹林を背景に、きれいに手入れされた樹木の緑が鮮やか明るい庭で関東関西方面より多くの人が訪れる庭である。 |
||
 |
||
| 鵜甘神社に古くから伝えられる面で県指定文化財。良質の檜材を用いて彫成され、寸法は面長24.5センチ、面幅18.5センチ、鼻の高さ17.5センチ。のびのびと屈託のない表情で、大からか気品が感じられます。 | ||
| 武周ヶ池 | ||
 |
||
| 野見岳(638m)頂上にブナ原生林に囲まれた池の周り(360m)は、年中変わらぬ水を湛え神秘的な雰囲気を漂わせています。 江戸時代には麓の上牧谷集落で道場を開いていた修行者の祈祷により雨乞いの儀式が行われたと伝えられ、現在でも毎年8月には龍神祭が行われます。 |
||
| 不動ヶ滝 | ||
 |
||
| 昔、この場所に不動明王が流れつき、滝の横に安置されたことが、名前の由来。春には周辺に桜が咲き乱れ、ハイキングスポットとして親しまれています。毎年7月の第3日曜日には滝祭が行われます。 | ||
| 孫嫡子神社 | ||
 |
||
| 719年、孫嫡子は奈良東大寺で出家、修行後、藤倉山に帰り、父から受けた如意輪観音像を奉じて、御堂を建て多くの病人を癒した。この神社は昔から疱瘡を癒す神社として有名です。 | ||
| 特務艦関東遭難慰霊碑公園 | ||
 |
||
| 舞鶴行きの命を受けた特務艦関東が、吹雪と怒涛により糠浦海岸で座礁したのは大正13年12月12日のこと。その難を聞きつけた村人は、己の身の危険も顧みず必死に救護活動を行いました。 遭難地に程近い海岸沿いに慰霊碑公園には、当時の救護活動の様子が描かれたレリーフ(2.5×7.0m)が建てられ、当時日本の人々を感動させたこの事件を今に語り継いでいます。 |
||